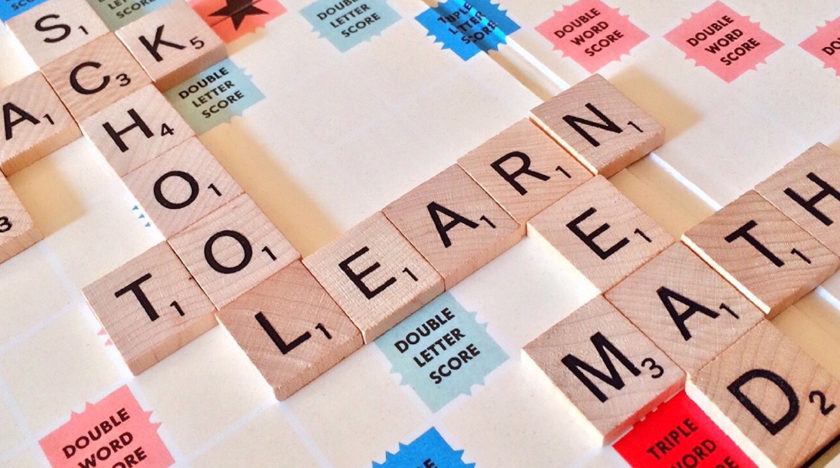次に2行目です。
One day he saw a man, Hyoju, by the river.
One day ある日(のこと)
he 彼は このheは誰のことでしょう。ここまでの登場人物はGonなので、
he=Gonとなります。「ある日彼は」
saw 見かけた sawはsee「見かける」の過去形
以上をつなげると、「ある日彼は見かけた」となります。
a 「ある」、「一つの」、「一個の」、と訳したり、訳さない方が良い場合もあり
ます。➡️ルール
ここでは訳しておきましょう。仮に「一つの」としておきます。
「ある日彼は一つの見かけた」
man 男(の人)。人が続きますから、「一つの」は「一人の」と訳し変えましょう。
述語動詞の後に名詞manがきています。この名詞は目的語という働きをし
ます。目的語が来たらその言葉に「に」や「を」のどちらかをつけます。
➡️ルール
「男に見かけた」「男を見かけた」ですが、この場合は「を」がしっくりき
ます。「ある日彼は一人の男を見かけた」
, Hyoju この「カンマ」はa manと兵十とが同じであることを表していますから、
「ある日彼は一人の男、兵十を見かけました」としておきましょう。
わざわざ「一人の」と訳さない方が自然だと思えば、「ある日彼は男、兵十
を見かけました」でもかまいません。
, このコンマも兵十の紹介の区切りです。
by〜 〜のそばで、〜のそばに 「ある日彼は男の人、兵十をみかけました、〜
のそばで」となりますが、「〜」がつく言葉(前置詞)は前の言葉a manを
説明するので先に訳します。➡️ルール
「ある日彼は〜のそばで男の人、兵十を見つけました。」となります。
the river theは「その」と訳したり、訳さない方が良い場合があります。ここでは訳
さずに進みましょう。
➡️ルール theは「その」と訳したり、あえて訳さない場合もあります。
「ある日彼は川のそばで男の人、兵十を見かけました。」
つまり、ゴンにとって兵十は顔見知りということがわかります。
Hyoju’s basket was full of eels.
Hyoju’s 兵十の 英語の名前’s=誰々の
basket 籠 「兵十の籠」
was であった。だった。 wasはisの過去形
動詞が登場したので、「は」を足しましょう。「兵十の籠はだった」
full of 〜 〜でいっぱい(の)「兵十の籠はだった〜でいっぱいの」ではなく、
「兵十の籠は〜でいっぱいだった」
eels eelsはeelうなぎ、の複数形 「〜」にこの「うなぎ」が入ります。
「兵十の籠はうなぎで一杯だった」
「うなぎ」が「〜」に入りましたから、ここで「〜」は消えます。
Gon crept up and let the eels out of the basket.
Gon ゴン
crept up crept up creptは creep(こっそり近づく)の過去形
「ゴンはこっそりと近づいた。」
and またandがでてきました。 crept upと次のletという動詞をつないでい
ますから、そのままゴンの動作として訳します。
「ゴンはこっそり近づいた、そして」
let させた 「ゴンはこっそり近づいた、そしてさせた」
the eels うなぎ(たち) 「ゴンはこっそり近づいた、そしてうなぎ(たち)を
させた」
ここも、動詞letのあとに目的語の名詞the eelsがきていますから、「を」
または「に」を名詞の後につけます。
out of ~ 〜から外へ 「ゴンはこっそり近づいた、そしてうなぎ(たち)を〜
から外へさせた」となりますが、ここはlet the eels out of~で「うなぎ(た
ち)を〜から外へ出してやる」と訳す方がいいでしょう。「〜」には後に
来る言葉the basketが入ります。
the basket 籠 「ゴンはこっそり近づいた、そしてうなぎ(たち)を籠からそとへ
出してやった。
“Stop!”
“Stop!” 動詞だけがありますから、これは命令文になります。➡️ルール
「やめろ!」
Hyoju shouted, but Gon and the eels escaped.
Hyoju shouted, 「兵十は叫びました」shoutedはshout+edで過去形。
訳に少しなれてきたと思いますので、ここでは2語をくっつけて訳し
ました。
but しかし 「兵十はさけびました、しかし」
Gon and the eels ゴンとうなぎ(たち) ここでのandはGonとthe eelsというふた
つの名詞をつないでいますから、「そして」よりは「と」のほうがいいで
すね。「兵十はさけびました、しかしゴンとうなぎ(たち)」
escaped 逃げた escapedはescape(逃げる)の過去形
動詞が登場しましたので、その前の言葉は主語になります。
主語には「は」または「が」をつけるのでしたね。
「兵十は叫びました、しかしゴンとうなぎ(たち)は逃げました」
第1節を訳しました。語順訳の練習ですから、単語や熟語の意味はぜんぶ与えられます。あくまでも訳になれること、訳に慣れて文の要素の働きを感じ取ることが大事です。そして、スラスラと音読することの大切さも述べました。
出てきたルールをまとめてみましょう。
1)主語には「は」または「が」、場合によっては「も」をつける
Jack plays baseball. ジャックは野球をします。
2)述語動詞(以下動詞と書きます)が出てくれば、その直前の名詞(句)が主語
Jack plays baseball. 動詞playsが現れたとき、Jackが主語だと判断します。
playsの原形はplay
3)動詞は日本語では最後に訳す
ジャック→ジャックはします→ジャックは野球をします
4)動詞の後にくる名詞(句)は目的語と言い、訳では「を」「に」を名詞(句)の後につ
ける。
Jack plays baseball. baseballが目的語 ジャックは野球をします。
5)to+動詞の原形〜不定詞と言って、以下の三つの訳し方があります。
〜するために、〜することを、〜するための、の三つのどれかに当てはめて訳します。
6)theは特定の名詞があとにくる。「その」と訳したり、訳さない場合もあります。
7)a(またはan)は単数名詞が後に来る。「ある」、「一つの」、「一個の」、と訳したり、訳
さないこともあります。
8)「〜」がつく言葉(前置詞)は前の言葉を説明するので先に訳します。
9)動詞の最後にedがつけば過去形。不規則な形で過去形になるものもある(不規則動
詞)。 例:look(見る)➡️looked(見た) creep➡️crept
10)動詞の原形で文が始まっていれば命令文。
Come here. ここに来なさい。 Stop!
英文の基本形式=語順は
主語→動詞→目的語または補語、という順序です。補語は文の中で主語や目的語を
説明する役割を果たす文の要素
Jack plays baseball. ➡️目的語
Jack is happy. ➡️補語
日本語の基本形式は
主語→英語の目的語または補語にあたる語→述語動詞 plays, is
語順訳をする、ということはどの単語も大切に扱い、語順に沿って日本語に変えてゆくとい
う作業です。単語に日本語の意味をあて、その意味だけを見て日本語らしい文になるように
つなげるのではありません。一語一語の関わり方を確かめながら前に進むやり方なのです。
そうして訳し続けることを通して、英語の語順に慣れたり、to不定詞の意味するところを
判別できるようになったりします。
単語や熟語は、それはそれとして覚えましょう。たくさんの言葉を知っていることは、語順
訳の作業をスムーズにしますし、将来、速読といって、英文を読みながらそのまま意味も理
解する、ということもできるようになるでしょう。 つづく