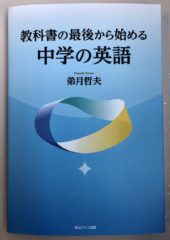
『教科書の最後から始める中学の英語』
- 弟月哲夫 著
- 青山ライフ出版
- 四六判
- 221ページ
- 定価 本体1500円+税
- ISBN 978-4-86450-463-8
- 2022年9月1日発売
著者からのメッセージ

英文の語順にそって訳す語順訳と音読について書きました。
教科書の物語作品を中学1年生の1学期の最初の授業日にいきなり読み始めましょう、というものです。
中学校でもぜひ実践していただければと考えております。
やった分だけ積み重なり、どのような生徒も決して挫折することない方法であると言えるものです。
ただ意味がつかめれば良い、読めればいいのではなく、語順にそって意味をつかみながら音読すること
が大事なのです。文法が苦手な生徒に易しい問題集を与えるのではなく、訳すのが面白い作品に挑戦し、
訳した後は、ひたすら音読をすすめるのが良い、と思います。文法が苦手な生徒は、文法以前にそもそ
も、「英語」というものに出会っていないのではないでしょうか。
「物語」はまず何よりも心に触れるものを持っています。会話の練習をするより前に、「英語」の核に
接し、「英語」を使っている人たちの息吹を感じ取れた時、学習のスタートラインに立てたと、言える
のではないでしょうか。
こんな方におすすめです
- 中学校の英語の先生
- 塾の英語の先生
- その他、教育関係者のみなさま
- 英語教育に関心のある保護者の方
- 英語教育を研究されている大学生の方
もくじのご紹介
- 第1部 語順訳と音読
- 1章 語順訳とはどのようなものか
- 2章 音読について
- 3章 作品として向き合う
- 4章 英作文と音読
- 5章 中学校でのグループ学習
- 6章 第1部のまとめ
- 第2部 言葉について
- 1章 規範について
- 2章 語順訳の価値は音読で決まる
- 3章 方法論
取扱書店
直接販売のほか、Amazonにて取り扱いいただいております。
直接のお申し込みは
e-mail otozuki@corelibrary.jpまで。お名前、お送り先、お電話番号、申込冊数を書いてお申し込みください。送料無料にてお送りいたします。同封の郵便払込票をお使いください。
著作のつづきとして
書籍を補巻する内容を当ブログに掲載しています。こちらも併せてご覧ください。
