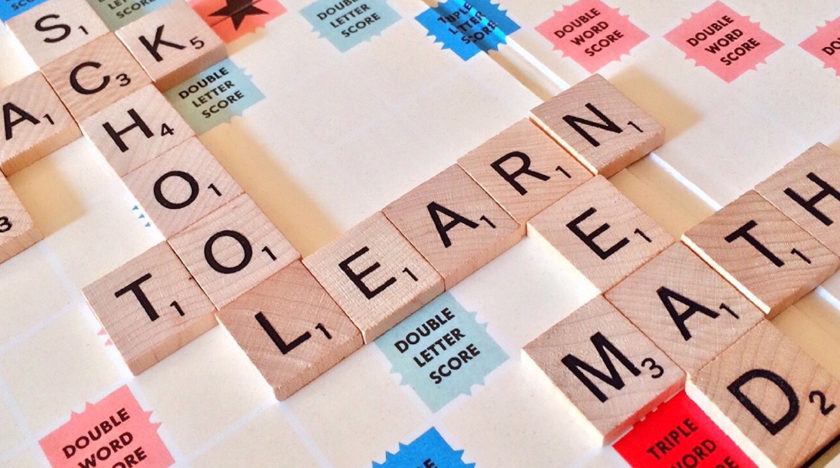Sleepy Lord Thunder NEW CROWN 1
今回はNEW CROWNの1年生の教科書からです。
語順訳を習熟すると、こうした文章も自分で訳せるようになりますよ。一部ですがやってみましょう。
Once upon a time, on Kohama Island, the sun was always bright, and the rain never came.The fields were dry. The crops were dying. The village needed rain.A young villager, Jira, visited the wise old man for advice. The old man said,“Wake up Lord Thunder. He makes thunder and brings rain, but he’s sleeping now. Make a big noise, and he’ll wake up.”
単語の意味、熟語はあらかじめ調べておいてください。また英文をスラスラ言えるまで音読してください。音読学習は英語の命です。訳の前もあともつねに音読ですよ。
では第1文です。
Once upon a time, on Kohama Island, the sun was always bright, and the rain never came.
英語の単語や熟語をまず声に出して読みます。それからその言葉の意味を言います。
次に単語の意味を言ったら前の言葉につなげます。
Once upon a time むかしむかし(ワンスアポンナタイムむかしむかし、と声に出す)
on〜 〜では 前置詞の後の部分には〜をつけます。(ここで「むかしむ
かし〜では」と言います。)
「〜」(ナニナニと呼んでいます)には後に来る言葉を入れます。
Kohama Island, 小浜島 この言葉が「〜」のところにはいります。
(むかしむかし、小浜島では)
the sun theとセットで、太陽
(むかしむかし小浜島では太陽)
was wasはbe動詞isの過去形で、「だった」。ここで動詞がでてきまし
たから、その前の言葉the sunが主語だとわかりますから、「は」
か「が」をつけます。ここでは「は」をつけて「太陽は」とします。
ルール:(述語)動詞が出てくればその前の名詞は主語。このあと
は述語動詞を簡単に動詞と呼びます。
主語には「は」「が」をつける。
(むかしむかし小浜島では、太陽はだった)
always いつも そのまま付け加えると、「むかしむかし、小浜島では太陽
はだったいつも」になりますが、日本語では述語(いた)は文の最後
にします。→ルール(むかしむかし小浜島では、太陽はいつもだった)
bright, 輝かしい (むかしむかし小浜島では、太陽はいつも輝かしいだっ
た)この「輝かしい・だった」を日本語らしくくっつけると「輝かし
かった」とか「輝いていた」になります。
このあとについている[,]は一応ここで文としての切れ目ですが、ま
だあとに続きますよという意味のカンマです。
and そして このandは前の文the sun was always brightと後の文
the rain never came.を繋いでいます。
the rain 雨 theは、決まったものについて、「その」と訳すときもあります
が、ここでは特に訳さないほうがいいでしょう。(そして雨)
never 決して〜ない (そして雨決して〜ない)
came. cameはcome(くる)の過去形。ここでは雨なので(降る)でかまわ
ないでしょう。これが動詞なのでその前の語the rainは主語。「は」を
つけてあげましょう。(そして雨はけっして降ったない→降らなかった)
あるいは(そして雨はずっと降らなかった)
The fields were dry.
The theが出てきました。決まったものについて、「その」と訳すこともあ
れば、訳さない方がいい場合もある。→ルールここでは「その」とつ
けておきましょうか。(その)
fields 田畑とか農地。(その農地)
were be動詞areの過去形。「だった」。動詞が登場しましたから、その前の
The fieldsが主語。主語には「は」「が」などをつけます。ここでは「は」
を選択しておきます。(その農地はだった)
dry 乾いた、乾燥の(動詞ではなく形容詞)(その農地は乾燥のだった)→
(その農地は乾燥していた)
あるいは(その農地は乾いただった→その農地は乾いていた)
The crops were dying.
The crops 穀物(穀物)
were dying be動詞wereとdyeの現在分詞dyingが一緒になって、
枯れかかっていた。動詞がきました、その前のThe cropsは主語。
主語には「は」「が」をつきますから(穀物は枯れかかっていた)
The village needed rain.
The village その村(小浜島の村)
needed 動詞needの語尾にedがついていたら過去形。
必要とした
動詞が登場したので、その前のThe villageが主語。主語には何をつ
けるのでしたか? はい、「は」や「が」ですね。
(その村は必要としていた)
rain 雨。動詞の後に名詞が来たらその言葉は目的語といって、語尾に
「に」または「を」をつけます。→ルール
雨→雨を(その村は必要とした雨を)日本語では述語は最後に訳し
ます→ルール(その村は雨を必要とした・必要としていた)
ここまでに出てきたルールをまとめておきましょう。
ルール①動詞が出てくればその前の名詞は主語。主語には「は」「が」をつける。
②日本語では述語は文の最後に言う。
③動詞の語尾にedがついていたら過去形。
④動詞の後に名詞が来たらその言葉は目的語といって、語尾に「に」または「を」をつけ
ます。
⑤前置詞の後の〜には後に来る単語を入れます。
⑥theは特定できる言葉につきます。「その」と訳す場合もあれば、訳さないことも
あります。
A young villager, Jira, visited the wise old man for advice.
A 一つのと訳したり、訳さない方が良いことがある。→ルール
ここでは「一つの」にしておきましょう。
young 若い(一つの若い)
villager 村人(一つの若い村人→一人の若い村人)
,Jira, ジラ(人の名前)“,”はA young villagerと同じものを指す引用符。
(一人の若い村人であるジラ)
visited 動詞visit(訪問する)にedがついて過去形となっている。
→ルール③ 訪問した。
その前の語(A young villager,Jira,)は主語。→ルール①
(一人の若い村人であるジラは訪問した)
the wise 賢い(一人の若い村人のジラは訪問した賢い)→ルール②
(一人の若い村人のジラは賢い訪問した)
old 年老いた(一人の若い村人のジラは賢い年老いた訪問した)
man 男の人 the wise old manが一塊でvisitedの目的語となっています
から、「を」「に」などをつけます。→ルール④
(一人の若い村人のジラは賢い年老いた男の人を訪問した)
(一人の若い村人のジラは賢明で年老いた男の人を訪問した)
for~ 〜を求めて(一人の若い村人のジラは〜を求めて賢い年老いた男
の人を訪問した)述語は日本語では最後 →ルール②
(一人の若い村人のジラは〜を求めて賢明で年老いた男の人を訪
問した)
advice 助言、アドバイス。「〜」にはこの言葉が入ります。→ルール⑤
(一人の若い村人のジラは助言を求めて賢明で年老いた男の人を
訪問した)
今回はここまでです。ルールが何度も顔を出します。でもやっていくうちに慣れてくると思います。繰り返しているうちに、主語、(述語)動詞、目的語といった言葉の意味がだんだんと身についてくるはずですから、焦らずにやっていきましょう。現在形と過去形の形が変わる動詞が登場しました。come→cameこうした不規則動詞と呼ばれているものの形は覚えるしかありません。過去分祠も一緒に覚えてしまいましょう。come /came/ come
語順訳のこと。わかりづらいところがあったら気軽に質問してみてください。(お問い合わせフォームを使ってください)、またお便りもお待ちしています。