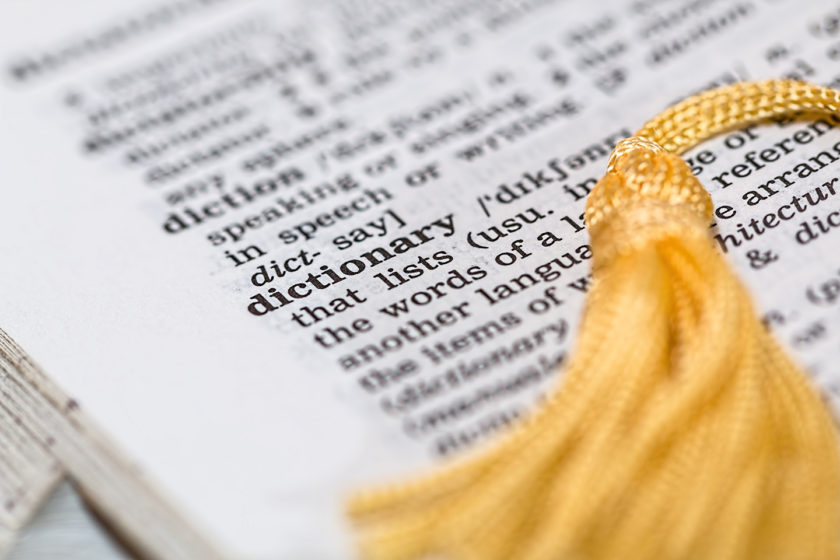生まれて間もない赤ちゃんには、確かに何かが目に映っており、耳に音が入ってはきている。そしてその世界は、保護者の目にも映り、耳に聞こえてくる音であることに変わりはない。
しかし、保護者の目に映るものは、ベッドであり、ガラガラであり、窓ガラスの外の木々でありと、そのほとんどは名付けられ、それぞれがなんであるかを本人は了解している。
語りかけている自分たちの声は言葉として表現され、意味が備わっていることを承知している。たとえそれが一見無意味と思える音声であったとしても、赤ちゃんに向かい、心を込めて発語していることに違いはない。だがしかし、対して、赤ちゃんにとってはそうした個々の存在は未分化であり、声は連続していて未だに区切りがつかない、そういう期間がしばらくは続くと言えるだろう。しかし、赤ちゃんはものすごいスピードで、世界を分割し始める。保護者の音声に区切りや規則を見出し、環境世界がものの名前に溢れて、それぞれに価値があるということに気づき、受け入れ始める。
これから私が述べたいことは、そうした赤ちゃんの生態ではなく、英語を学ぶ日本語話者としての子どもたちについてである。
似ているところがあるのではないか。赤ちゃんが母語を獲得する特性に近い状況を生み出せれば、英語学習も少しは効率よく学べるのではないか。
海外生活という場合を除いても、学ぶものの環境条件を限りなく広く取れば、おそらくほとんどの人は英語を学習し、獲得するだろう。つまり、学習しなければならない必然性があり(たとえば家
の隣に英語話者の家族が移り住み、家族ぐるみの交流があるとか、英語話者が身につけている特技があり、自分もそれを身につけたく思っているとか=目的がある)、学校の勉強といった強制によるものではなく、自分から意志を持って学ぼうとしている場合、学び方により効率の差は出るだろうが、いずれは習得すると言えるのではないだろうか。
しかし、一般的な子どもたちの場合、この「必然性」や「意志を持って」ということが欠けている場合が多い。つまり学校での、教科としての英語となると、義務感や成績への意識がいつの間にかやってきてしまう。
習い始めこそ、興味津々で積極的だったものが、ある時から色褪せてきて、問題集を解くことが学習であるとなりがちではないか。学校では場面ごとの会話のやりとりの練習もあるだろうが、練習さえすれば、すなわち英語力が備わる、というのとは少し違うのではないか。
例としての会話文を覚えても、さらに前に進めるというわけではない。
勝手に応用力がつくわけでもない。
赤ちゃんの例で言えば、保護者とののっぴきならない関係の中にいるからこそ、音声に区切りや規則を見出せるのであって、自分に無関係に話されている言葉は雑音に過ぎない。この音声は大事だ、という思いが隠されているのはいうまでもないだろう。自分の生活と無関係に「まど」や
「にんぎょう」という言葉を覚えるわけではない。「ママー」や「ブーブー」の延長として訪れて来たものを分節化していくに違いない。
身の回りのそれらは「かけがえのない」ものたちなのである。
英語を学習対象として学んでいる子どもたちにとって、すべてを「かけがえのない会話」「かけがえのない単語」にすることはとても大変。
赤ちゃんが自分を取り巻く環境を意味や価値あるものとしてとらえているのとは大ちがい。バラバラの知識に統一感を持たせ、確かな英語の世界を築き上げる必要がある。たとえ知識が曖昧であっても、英語という世界の「感じ」をつかめるようにしなければならない。
「物語」の世界は、赤ちゃんの世界とはもちろん異なるけれど、心を奪われる世界であることは間違いないだろう。たとえ、そこで科された学習が語順訳や音読であっても、背景の物語の世界は、子どもたちの心のどこかに引っ掛かりを与えるだろう。どの単語も、どの一文もその物語にとって不可欠で、かけがえのないものなのだから。
英語学習するものにとって、場面が日常的でわかりやすいことが魅力的なわけではない。その先にどんな展開があるかという、謎めいたところを残した世界にこそ惹きつけられると言っていい。
赤ちゃんにとって、初めはその世界がすべて謎であるのに似ているかもしれない。