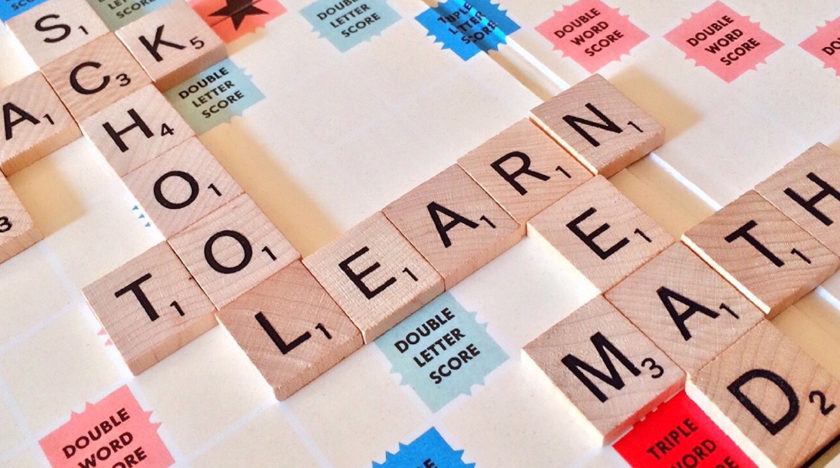選択するということ
前回のことを、少し詳しく述べてみます。
言葉が生まれてくる場面を考えれば、まずその言葉の話し手がいて、聞き手(一人かもしれないし、複数の人たちがいるのかもしれません)がいます。
それから、目の前に一人「彼」だけがポツンといるのではなくて、周りにほかの人がいるかもしれない。そして、その中から「彼」を選び取っている状況であると書きました。
日本語では、「放課後野球する?」「するよ」といったふだんの会話では、あまり「主語」は使いません。「放課後、君は私と野球をしますか?」「私はあなたと野球をします」とはふつうは言わないでしょう。
しかし、英語の基本は違います。主語を言わないでいきなり Play baseball after school.では命令文になってしまい、意味が変わってしまいます。返事もただ、Play(Do)とは言いません。
何かについて発表したり、説明したりする時には、「誰が」「何を」「どうした」と言うことをはっきりさせて言いましょうと言われます。
どちらかといえば、英語はその形式に似ています。
何かを説明する時や、物語を語る時は、ふだんの会話と違って、私たちは言葉使いを変えます。
前者では、聞く人、つまり他人の存在を強く意識します。
そうでないと物事が正確に伝わりません。
でも会話では、話し手と聞き手が一緒にいるわけなので、仮にうまく伝わらないことがあっても、すぐに修正することができます。
また、言葉の調子や身振りから、その背後にある思いも感じとれます。
言わば、お互いに環境や情報を共有しているから、言わなくても済んでいることが多いのですが、
英語ではどのような場合でも、原則は「主語」とか「所有格」とか「述語動詞」を抜かさない、ということになります。
つまり、主語が「彼ら」なのか、「私たち」なのか、「私」なのか、あるいは「あるもの」なのかを選び取るということが求められるのです。
このように、日本語の会話ではあいまいに、主語も目的語も言わずになんとなく話していても、通用しますが、英語を話したり、書いたりするときは必ず物事をはっきりさせる、という態度が必要になります。
「放課後、君は私と野球をしますか?」という文は、日本語の会話文としては堅苦しいものです。しかし、英語を使うときは、「君は」「私と」といった人称を意識しないといけません。つまりは、日本語話者同士の会話のように「堅苦しいことは抜きにして」という意識を捨てるということになります。
日本語話者であることから、英語話者へと飛び移らないといけません。
上手、下手を別として、まず意識を切り替えることが大切なのです。
教科書にかぎらず、物語作品を語順訳すると、その切り替えが自然にできるようになります。英語の物語世界の中に入り込むわけですから心が自然に英語になじみます。登場人物ABC…のどの言葉にも入り込めます。
物語は日本語から英語へと自然に飛び移れるような世界なのです。
自分がわかる範囲で読み物を読むのではなく、それ以上の作品に挑戦してみる方が、あなたの英語力は確実に高くなるでしょう。
そうすれば、教科書のどのような英文も、今よりずっとやさしく見えるに違いありません。
英語が「わかる」ということは、テストで問題が解ける、ということを必ずしも意味しません。比較級の場合にはerをつけるということは英語の一つの規則にすぎません。規則をどんなにたくさん覚えてもそのことでわかることは、「英語の規則」であって、英語という言葉そのものではありません。
本格的な物語作品を訳していくうちに、あたかも登場人物の一人になったような気になることがあります。
会話や英作の場面で、youやmyといった人称代名詞が、いつの間にか自然と口をついて出てくるようになったとき、「わかった」と叫んでいると思いますよ。