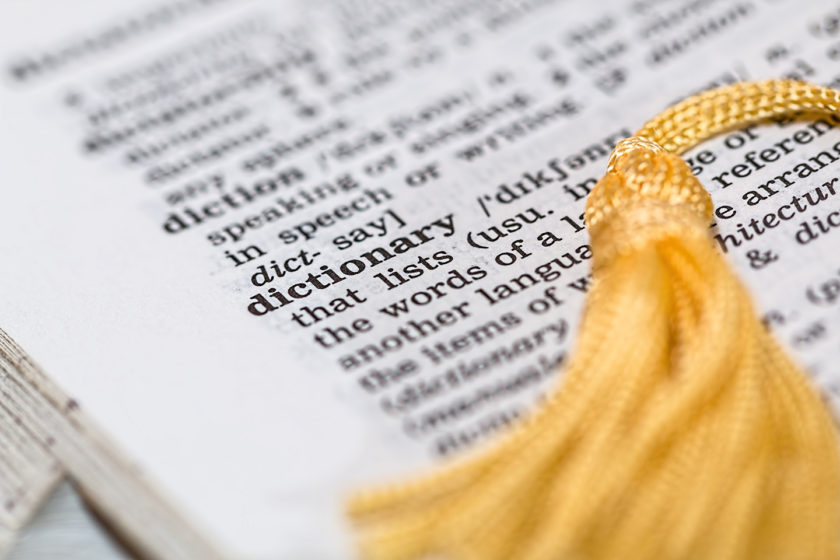英語の中学教科書に対して、何が不満かというと、原作のある長文作品―主に物語作品ですがーを簡略化して載せる場合、限られた文法の範囲内であることに加えて、単語、熟語も制限して使用していることです。できる限り原作を活かす以前に、まず枠があり、そのために作品にそれほど現実感が出ていないのではないかと思われます。
すべてとは言いませんが、作者にとって大切と思われる表現や語彙はできるだけ使えばいいのではないか。それを知識として覚えるように強制しなければいいわけです。しかし、訳をするときには原文の味わいを残しておきたい。
生徒たちにとって、世界は年齢に合わせて立ち現れてくるとは限りません。むしろ風のように、そのまま、つまり生のまま訪れることが多いでしょう。知らない言葉、知らない概念、理解を超えた言葉使いなどザラです。だからこそ、知りたくもなり、理解しようと努力する糧にもなります。習うことは学年に応じてとなるでしょうが、世界はその先に奥行きを持っており、謎めいていて、いつも理解を超えているのではないでしょうか。だから面白い、とも感じるのです。
弊社の生徒たちは、文法もわからないし、助動詞の使い方、現在完了形の意味合いも知りませんが、小学高学年から長文に向き合います。中学生段階でも出てこない構文であっても、訳のルールに従って語順訳を実践しています。理解しなければいけないレベルは人それぞれだし、ましてや覚えないといけない事柄は限られています。それでも作品の中心に向かって突き進むことができています。
トラが貧しい男に言います。(The Slow-Witted Jackalより)
I want to eat you.
You don’t want me to eat you.
Who is right, you or I? Hmmmm…?
We shall ask the first three things you choose.
We’ll do as they say.
そこで貧しい男は、尋ねる相手を見つけようと歩いて行きます。そして
First the poor man asked a linden tree that stood
casting its shadow on the land.
こういった文を、四苦八苦しながら訳します。
不定詞も助動詞も関係代名詞も出てきますが、おかまいなしに進めます。その訳や使い方を教えてしまえばいいのですから。こうした方が英語の全体像を早くつかめる、そのように考えてのことです。