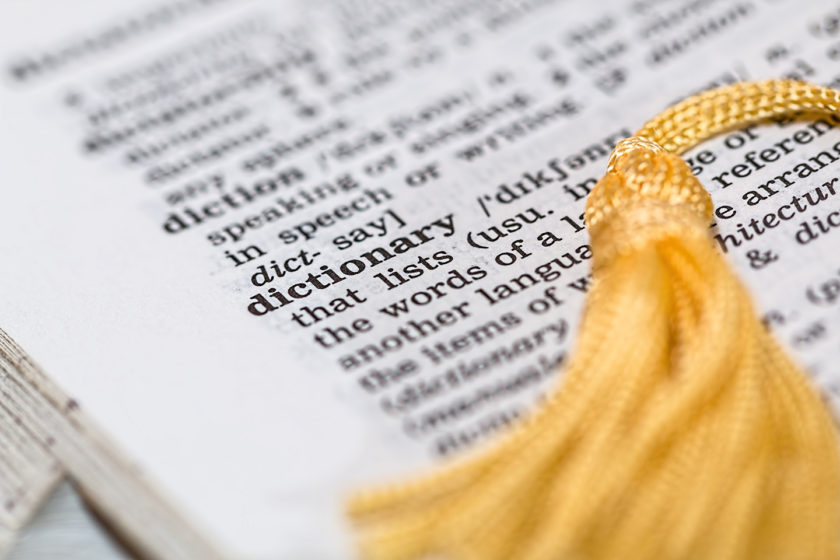中学生段階での英語学習のはじめ指導者にとって一番大切なことは、個々の文法事項の理解を求める以前に、まずはすらすら読める音読を求めるべきでしょう。
その上で、語順への意識を育てるということではないでしょうか。
英語の語順を遵守する意識の強さを育てると言ってもいいかもしれません。
日本語と英語では、語順が逆になる場合がある、そう説明され、そのように覚えることと、そのことへの強い意識をもつということは一見同じに思えますが、ただそのことを記憶し、問題に向き合うときに思い起こし、正解にたどり着くのとある内容を英語で言おうとしたときに、自然に、主語→述語動詞へと語順が決まることは決定的に異なると言えるでしょう。
記憶を参照しながらの英作から、語の関係を意識した上での英作へと推移するためには、どのような訓練が必要となるか。
語の関係が身体化する、内在化させるためにこそルールに則った語順訳を繰り返し、意味をとらえた文章の音読が必要になるのではないか。
語順に沿った訳の作業は、英語と日本語とのぶつかり合いです。
語順が比較的ゆるやかな日本語に変換しようとして訳の語順を間違えることが多々あります。そこを英語の語順を優先させて訳すことを要請するわけですから、混乱を来します。
その混乱が、生徒の言葉を育てます。受け身ではなく能動的な間違いだからです。なぜか、語順訳への意識を育んでいるようです。
記憶された規則を常に参照する場合、ある内容を表現するという意識は低いと言えます。それに対して、語順が身体化されていて、自然な行為として語順が決まる場合、(私たちの生徒の場合)何よりもまず「あることを言おう」としているように見受けられます。
そして、そのあることを言う以前に言葉の背景を想像できている、すなわち、場面を思い浮かべている、と言えるようです。
自分が語り手であると位置付けられ、言葉を音読している、そのように言いかえてもいいでしょうか。