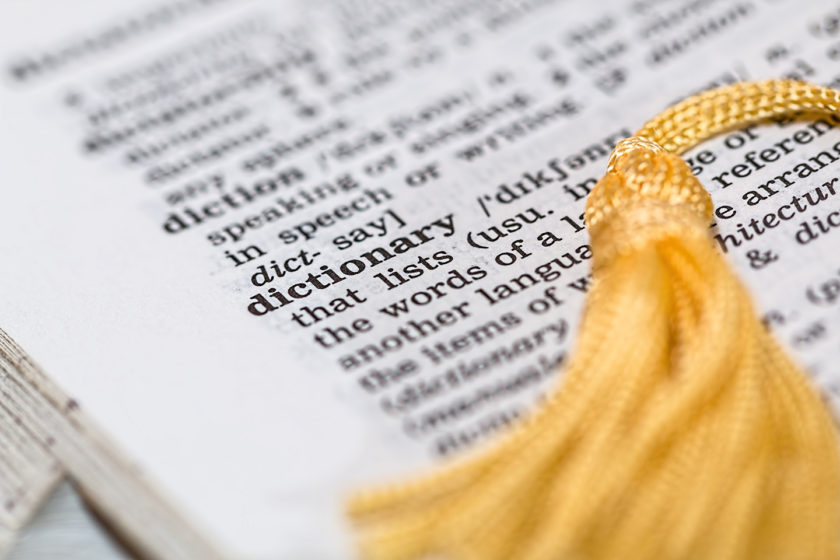生徒たちの音読の進捗は、指導者が各生徒の目標値をどこに置くかで左右されるのではないでしょうか。目的地を与えることはとても大事なことだと思います。
ところで、文法学習の理解の度合いは、能力というより、個々の生徒の成長によって決まるのではないか、そう考えられます。みんな一緒に、というように足並みを揃えるのはたいへんむずかしい。しかし生徒の側からすれば、文法学習は目に見えるものなのでとっつきやすいし、何問解いたぞ、というように自己満足にもつながる。結局は問題集をこなし、テスト対策をしようとすれば、どうしても音読は二の次になりがちか、無視してしまうことになるでしょう。問題を解くと、その分、前に進んだように感じられ、即効性があるようにも思えるからです。しかし、文法の全体を知らない者が部分的な知識を理解しようとしても、どうしても無理があり、わかったような気がする段階に留まっているように見えます。ただ問題に慣れただけかもしれません。問題に慣れ、テストでは記憶を頼りに解答をともかく出して、それが正解であれば、英語ができたと思うわけです。しかし、それほどことは甘くなくて、応用問題や長文問題になると実力が問われ、今度は、自分は長文が弱いとなる。英語がわからないのではなく、長文が弱い。そこで、今度は長文問題集をやるとか、そのような対応を求めて塾へ通ったりします。
今、私は、一部の頭の良い生徒、自分で学習範囲を広げて英語に触れることのできる生徒について書いているわけではありません。過半数の、将来英語嫌いになるかもしれない生徒を思い浮かべているのですが、文法についていけなくなりがちな生徒こそ、音読の徹底が必要だと言いたいわけです。文法の世界に関してはたくさんの時間を要し、学校の進行よりゆっくりとしか歩めない生徒。英語の世界のどこを、今歩いているのかが見えていない生徒を思い浮かべて、これを書いています。課題はそこにしかありません。できる生徒はできるのですから、ほっておいていいわけです。
文法学習を一つの理論的な体系の世界と見做せば、そのような領域が弱い生徒こそ、音読を徹底すべきだと思います。読むのが下手、そもそも読むのが嫌いと感じて、すぐ問題に取り組む生徒は、読めないのに、つまり、英語とは言えない読みをしておきながら、英語の問題を解くという矛盾にはまり込んでいます。そういう時、目の前の文法説明が大事なのでなく、行き先を示してあげることが大事だと思います。今どこにいて、これからどういう場所を目指しており、その気があれば、「君はそこに行ける」と言ってあげることです。自分で文法書を読んでわからない生徒は、どんなにやさしい言葉で、たくさん比喩を使って説明しても、わかるものではありません。説明は下手をすれば指導者の自己満足に過ぎないとも言えます。そんな生徒に必要なことは文法ではなく、体験なのです。スラスラと読める。英語らしく言える。自分の言葉のように英文が読めた時の快感なのです。素振り練習のおかげで、バットにボールが初めて当たる、その時のうれしさこそだいじではないか、そう思うのです。
He was so proud of his daughter that one day he spoke to the King about her.
たとえば、この箇所を語順訳するとします。
まず読みます。声に出して読むことから始めます。スラスラ言えていればよしとします。
それから語順訳します。次のような経過をたどります。
彼は
彼は〜を自慢に思っていた
彼はとても〜を自慢に思っていた
彼はとても彼の・を自慢に思っていた
彼はとても彼の娘を自慢に思っていた
彼はとても彼の娘を自慢に思っていたので
彼はとても彼の娘を自慢に思っていたので、ある日
彼はとても彼の娘を自慢に思っていたので、ある日彼は
彼はとても彼の娘を自慢に思っていたので、ある日彼は話した
彼はとても彼の娘を自慢に思っていたので、ある日彼は〜に話した
彼はとても彼の娘を自慢に思っていたので、ある日彼は王様に話した
彼はとても彼の娘を自慢に思っていたので、ある日彼は王様に〜について話した
彼はとても彼の娘を自慢に思っていたので、ある日彼は王様に彼女について話した
途中では、何度も間違いを訂正されたり、訳ルールの確認をさせられたり、右往左往しなが
ら進行します。決してスイスイいくわけではありません。そのつまずきが、また生徒を強く
します。言葉の訓練になります。自分の発言した言葉を振り返るということは、考える力を
相当つけているはずです。
さて、この息の長い文でも一文としてつないで訳をします。
このようにして全文を語順訳したあと、もう一度音読練習をします。
復習として(自宅学習)、スラッシュ単位の意味を確認したり、とにかく繰り返し音読練習をします。
つまり順序に沿って日本語にせずに意味を了解できるようにし、翌週には、カナフリのないテキストを使って音読をさせます。
全文を訳し終えると、役割を分担して、劇練習に入るのですが、この段階では、各語の発音を間違えていたり、平板な読み方だったり、そもそもつっかえたり、などということは少なくなっています。
つまり、一応語順訳と音読をやりました、はい次の作品、ではなく、必ず目標とする姿(劇発表)を追いかけます。学んだことの一応の集大成があります。この最終形がないと、生徒はどこに向かっているのか、どんな場所に行きつけば良いのかがわからなくて、途中の学習の意義が薄れるでしょう。
野球のボールを受ける練習をしていて、繰り返し失敗したなら、失敗しないための練習をします。失敗しない水準が目標となるわけです。英語学習でも同じではないか。読みが下手なら練習する。練習を積めば、必ず音読の質は上がります。
多人数の授業で全てはできないとしても、読みの水準を上げるために目標課題を出すことはできるでしょう。そしてそれを自習として行うようにもっていくには、どんなにささやかな変化であっても、そこを肯定してあげることだと思います。
整理しますと、語順訳の進行に沿って、音読にはいくつかの段階があることがわかります。
意味把握:①語順訳→②語句単位で意味がわかる→③日本語にしなくても語句の意味がわかる→④文全体の意味が直接わかる、イメージできる
音読の質:⓪カタカナ読み(日本語)→①スラスラ読める(正しい発音)→②見本音声のイントネーションを真似することができる→③見本音声全体の模倣ができて、同じ速さ(あるいはそれ以上の速さ)で言える。→④話し手になったつもりで言える訳と音読の①→④は必ずしも並行しているとは言い切れませんが、同じように歩んでいるかのようには見えます。
著作の本文中で、「閾値」という語を使いましたが、生徒の様子を見ていると、はっきりとした線引きができるわけではありません。ある水準を超えたな、と感じられる読みが達成できた時、生徒は英文を自分のものにしたと、言えるのではないでしょうか。いわば連続したグラデーションの世界を移行している状態と言えるでしょう。ある文ではできても、次の文はできていないということもありますが、いったん閾値の感覚を得た生徒は、英作文の時(小学6年生)でも、頭や記憶で考えるというより、むしろとにかくある文を産出する、つまりは即答できるような作文感覚に繋がっていくようです。たとえ解答が間違っていても、何かを直接英語の文にするという作文感覚です。小学生の時の音読で養成されたものが、中学2年から3年生になると、さまざまな領域で生きてくるといった感じです。中3で英検2級が現実的な目標となり得ます。繰り返しお伝えしたいことは、音読はどのような生徒でも挑戦できることであり、やった分だけ必ず成果が出る、ということに尽きます。
従って学校教育でも、小学生段階で物語作品の訳と音読を、もちろんやってみたいものです。
学校間の接続が叫ばれていますが、小学生で物語の音読のたまりを蓄積できれば、中学校ではより幅広い学習が期待できるのではないでしょうか。
(つづく)