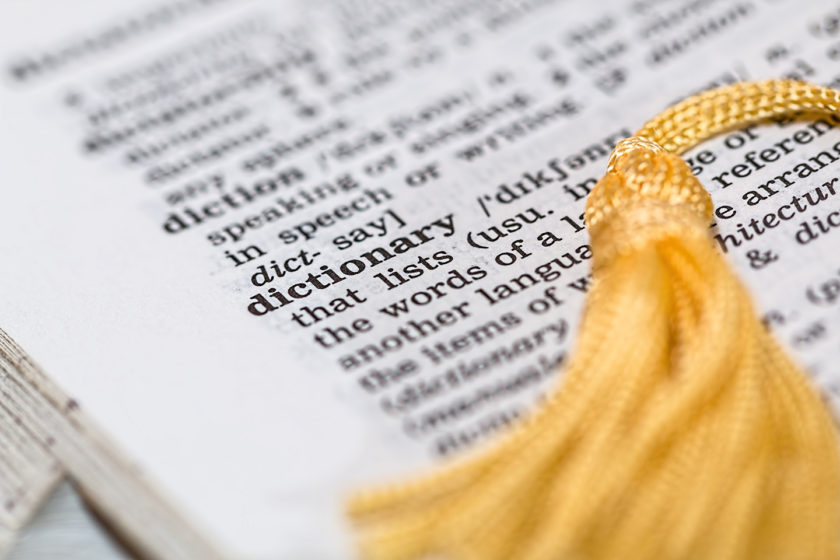中学生の英語学習では、いつの間にか前提として受け止められていることがあるように見えます。それは、英語から日本語へ、あるいは日本語から英語へと変換する場合、言葉は一対一に対応しているという、どちらかといえば無意識に捉えているのではないか、ということです。習い始めた途端に、いつの間にかそのように思い込んでしまっているのかもしれません。対応しているからこそ、学ぶことができる、というように。
何か一つの単語を辞書で見てみるとすぐにわかるように、さまざまなニュアンスがあり、訳語が当てはめられ、その語の意味や働きが蜘蛛の巣状に広がっていることがわかります。学習の初めからそうした複雑な情報全部を相手に出来ませんので、一つの単語を一つの日本語に当てはめることが多くなるでしょう。I am〜という文型もそれに拍車をかけているかもしれません。日本語に訳しにくい文で学び始めるのではなく、わかりやすいものから、という発想は、そのことを助長しているように思われます。
しかし、いつの間にかいろいろな面で英日が一対一に対応していると思ってしまうと、都合の悪いことが起こります。よくあることですが、「〜が好き・です」という形式の文を英語にするときに、likeとbe動詞を併用してしまうことがあります。一般動詞とbe動詞の働きがまだよくわかっていない、というように判断されてしまうのでしょうが、英語の動詞にはその2種類があると説明を受けたにもかかわらず、間違いが起こります。英語の動詞にはそのような区別がある、つまり英語の世界の話として受け止めるしかない、にもかかわらず、間違える。つまり心がその事実を了解することにどこかで抵抗している。日本語にはそれに対応するものがないので、本当は説明を受け入れられないという状況が起きているのではないでしょうか。そのことをすんなりわかってしまう生徒と、そうでない生徒がいるでしょう。
それは頭の良し悪しなんかではなく、言ってみれば、日本語から離陸できているか、できていないかの差ではないか。それがなぜ起こるのかはわかりません。生徒の心の中を解析できませんから、こうだとは言いきれませんが、英日が対応しているとの思い込みが強いのかもしれません。あるいは、そもそも心が英語学習に十分に傾いていない、ということも考えられます。
こうした現象は、英作時の語順がいつまで経っても出鱈目なことにも現れたりします。とにかく、英日が対応しているという幻想から解き放ち、英語の世界へ入って来るように導いてやらなければなりません。
生徒の中には、英語を将来使えるようになりたいとか、趣味の世界の英文を自分で読めるようになりたいとか、積極的な姿勢の人もいれば、テストの点数を気にして問題集ばかりやる人もいるでしょう。また、とにかく学校の授業なので受けているだけという人もいると思われます。指導する側としては、どの生徒も同じように導いていきたいと思ってはいても、なかなかそうはいかないのが現実でしょう。
授業の枠組みを壊さずに、予定通り前に進むほかないでしょうから。英語の世界に関心を持ち、外国の人たちとのやりとりに思いを馳せてほしい。日本語とは異なる言語に少しは関心を持つと同時に、日本や日本語を振り返る機会を持ってほしい。他者への関心を深め、想像豊かに物事を考えるようになってほしい。英語の理解度は、生徒によってさまざまであっても、指導者の方は、そのような思いをもって過ごされているのではないでしょうか。
さて、一対一の対応意識を引きはがし、まずは英語そのものに心を傾けるにはどうすればいいのでしょうか。私たちはそれを「物語」を語順訳し、音読することで解決しようとしています。
もちろん学校と異なり、自分から(あるいは親に誘われて)私たちのところへやって来る子どもたちですから、多くの生徒は前向きではあります。でも中学生になると気になるのは学校の成績です。学校の成績が良くなることを願うのは、もちろん本人ばかりではありません。親御さんはいうまでもなく、指導者もまたそうです。しかし、私たちが力を入れるのは、物語長文の語順訳であり、音読であり、英作です。問題集は控え選手です。語順訳で英文の語順感覚、文の要素の配置感覚を養い、そして何よりも英文のテンポ、リズム、イントネーションが生み出す力動感を手に入れるための音読が最重要です。この力動感を手に入れると、英作をする場合も、まずあることを話そうとする、伝えようとする感覚が生まれるように思われます。知識を思い起こし、文を作るというより、その基底には、とにかく言葉を生み出そうとする感覚があるようです。もちろん初期(中1〜中2)では間違いも多い。目的語が最初にきたり、動詞を見誤ったりします。「英語の動詞にあたるのはどれ?」とか「だったらその前に主語がくるよね」などとアドバイスすることはたびたびです。一般動詞とbe動詞の場合の他にも、目的語と述語動詞の位置が逆さまになったりします。そこをただ不正解、などと言って終わらせるのではなく、淡々とやりとりします。そしてたくさんの英作をしているうちに、知識としてというよりは、心や身体がルールを身につけていくかのように、できるようになります。船が揺らいだときに元に戻ろうとする復原作用が働くような感じ、とでも言えるでしょうか。英作してはみたものの、何かがおかしいという感覚があるので、ちょっとしたヒントで修正が可能になります。
知識を獲得するには、頭が理解することと、心や身体が受け入れることの両方が必要な気がします。どちらが先ということはありません。生徒たち一人一人違うでしょう。ただ言えることは、知識に弱い生徒ほど語順訳と音読をした方が良い、ということでしょうか。知識を身につけさせるためにそれをするのではなく、ひたすら淡々とシンプルに、指導者と生徒との間でやりとりする、ということです。バットを繰り返し素振りすれば身につくものがあるとすれば、訳と音読はその素振りだといえそうです。
英日が一対一に対応していない、その最たるものは、日本語は語の順序に対して寛容だということでしょうか。述語が最後に来る感覚のもとに文を作ります。主語も目的語も副詞もどう並べようと述語につながりさえすれば、一応文は作れる。この寛容さを括弧の中に入れてしまわないと英語にはついていけません。
しかし、英語では語順が大事なのだと言われても、なかなか納得できないのがほんとうのところだと思われます。言葉の表現には意味と音とが現れます。意味だけを追いかけていても、言葉を解ったことにはなりません。音から伝わってくるものもまた、心や身体が受け止めなければならないでしょう。英語の主語→述語動詞→目的語と前に進んでいく力動感には意味の積み重なりと、音の流れとが含まれています。語順が異なるだけではなく、英日ではこの力動感が違うということを、今以上に体験することが必要なのではないでしょうか。知識としてではなく、一つの息の長い文の音読を通して、語順を体感し続けると、日本語から離陸できるのではないでしょうか。
一対一に対応していない言い方に触れているにもかかわらず、心のどこかで英日が対応しているように思い込んで向き合っている、そのことで英語が分からなくなり、やがては苦手な科目へと転じさせているように思いますが、どうでしょうか。対応している部分もあれば、対応していないこともある、というのが正確な言い方だとは思いますが、その境目がどこであるとは言い切れませんので、あえて対応していないことを強調して述べてみました。
(つづく)