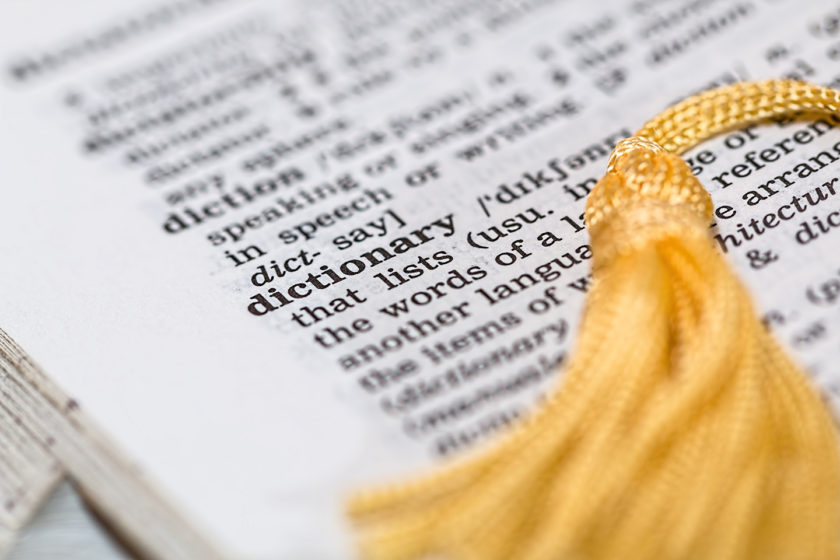Once there was a miller who was very poor,
but he had a very beautiful daughter.
このテキスト‘Rumpelstiltskin’は小学生の高学年で取り上げる作品なので、ほとんどの語句には意味が書かれています。
Once(むかし) there was(いました) a(冠詞の説明あり)
miller(粉屋) who(関係代名詞の働きの説明あり)
was(だった) very(とても) poor(貧しい)
but(しかし) he(彼は) had(持っていた) a very
beautiful(美しい) daughter(娘)
そして前半は次のようにつなげていきます。
むかし
むかしいました
むかし粉屋(が)いました
a millerとwas very poorに下線を引いて、「whoは関係代名詞と言って二つの語句を結びつけている」ということを説明します。
(むかし粉屋がいました。だった)としがちなのを訂正して、was very poorがa millerにつながることを繰り返し言います。
むかしだった粉屋がいました
むかしとてもだった粉屋がいました
むかしとても貧しいだった→むかしとても貧しかった粉屋がいました
この作品は語順訳の2作目として使われることが多いので生徒たちはかなり語順訳になれている状態であると言えるでしょう。
「英語の主語を日本語にする時には『は』や『が』をつける、とか、冠詞aは単数名詞が後にきて、『一つの』『ある』『訳さないことがある』」などいくつかの訳ルールもある程度頭に入っている。
ここに登場する「関係代名詞」も、あくまでも訳をするために、語句のつながりを説明するのであって、それを使いこなせるようにするわけではありません。
wasも過去形だから、その前に現在形を説明し、慣れさせるなどということはありません。現在形、過去形いずれが易しいかなどということは、まったく問題になりません。
この作品の第1行目から、物語は始まり、クライマックスを経て、終盤へと向かい、やがて物語は終わります。
生徒たちは文法例文を訳しているのではありません。
ある物語が今から始まるということを、漠然とではあっても感じ取っているでしょう。訳自体は作業ですから、四苦八苦し、主語や述語動詞といった言葉が飛び交い、それどころではないかもしれませんが。それでも一文を訳し終えれば、スラスラと言える音読が求められます。意味了解はかすかかもしれませんが、とにかく文を声に出して読みます。
文が繋がっていくに従って、物語のイメージがふくらんでいきます。
いわば表現としての英文に触れていくわけです。
一方では個別の文を語順訳し、まとまりを持たせようとして日本語と格闘し続けます。時にはまったくデタラメに「を」や「が」や「に」をつけてわけがわからなくなる時があります。そうした時には、初めに戻り一歩ずつ訳し直して、ようやく一文を終えることになります。
こうした混乱はいつの間にか収まり、いつしかスムーズに訳せるようになっていきます。とても不思議な現象ですが、英日の語句の運びの違いに慣れていきます。易しいものから難しいものへといった一般的な順序とは異なり、物語の表現が自然に感じられる文章では、さまざまな文法の事柄が登場します。そのことがかえって、英文のイメージ作りに役立っている、英語の語順の感覚を養っていると考えられるのです。
易しいものから始まる英文法の例文を同じように訳したとしても、このような成長は望めない気がします。
物語という表現の世界全体との関わりがあってこそ、訳をする意味があると言えるのではないでしょうか。
Once there was a miller who was very poor,
この一文が関係代名詞を学ぶための文法例文だとすれば、訳した時、whoの働きに目がいき、文全体をイメージするという行為はどうしても弱くなるでしょう。誰の、誰に対しての文であるかも、
そこでは問われません。
この文を表現として見るとは、語り手が読者である自分に語りかけているという関係を受け止める、ということを意味します。
語順訳という単純な作業、技術としての訓練が、物語の表現という全体に包み込まれているからこそ、英語の語順感覚を手に入れることができていると言えるように思います。
語順訳という個別作業の積み重ねが、そのまま英語力につながるのではなく、音読を介して、全体を表す作品世界へと飛躍する経験が英語力を育てている、そのように考えられます。
物語を語順訳する意味